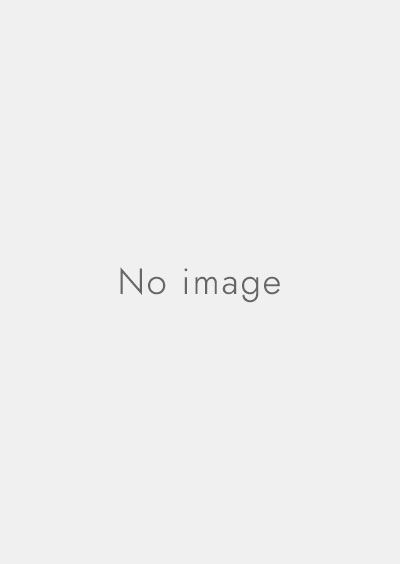現実世界のつながりを絶たれた時代が終わろうとしていた。多くの人は喜んで太陽の下へと駆け出したが、"むこうのくに"に残ることを選んだ人もいた。そこは、画面を一枚隔てれば、生まれた場所や話す言葉、ヒトかどうかさえも関係ない、現実のしがらみが無効化された世界。その夏、ぼくは相変わらず画面の前に居て、"むこうのくに"へアクセスしようとしていた。行方をくらませた、"ともだち"を探すために——
なんでだろう。この部屋が、どうしても嫌いになれない。繁華街に佇むそのアパートの一室は、隣に建った看板のせいで窓からの眺めがまるで見えなかった。毎夜看板の光が色とりどりに揺れるその部屋で、伊野夏子は死んだ。二十歳を迎える少し前に、彼女はしずかに幽霊になった。数年後。そこに引っ越してきた津島一郎に自分の姿が見えていることに、夏子は気付いた。一朗は恋人を持たず、友人も少なかった。夏子は彼を気に入った─約