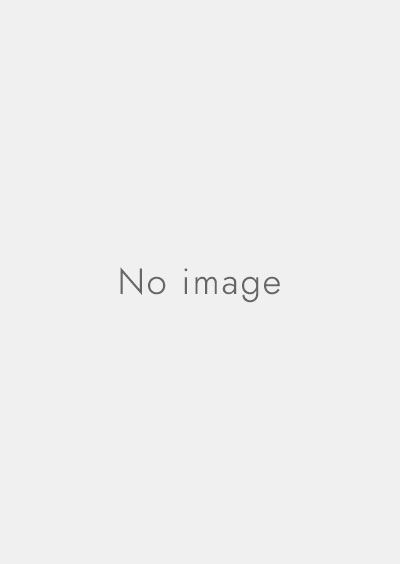—何したっていいだろう、たった七日なんだから—八月、陽の光に強く照らされた猛暑。彼らは鳴き続ける。この世に生を受け、年月を重ね、やっとの思いで地上に姿を現したのだ。自らの身体の形をした殻を残し、大空を飛び回り、そして必死にしがみつく。休むことなくひたすらに鳴き続ける、大きな声で。彼らの晴れ舞台。たった七日で何ができるだろう。強く、強く、鳴き続ける。
(チラシより)いつだってずっと、もう何年も。どこか内側に在るシーンというシーンは、眼裏で目まぐるしくリフレインしている。最速のスピードを持って、脳内を駆けめぐる。あの季節の、あの湿度のなかを走りつづけている。もしくは、歩いている。校舎のなかを。休み時間、教室から教室へ。廊下を、歩いている。なんともない日々の眺め。しかし、その平穏さが一変する瞬間。いつのまにか忍びよっていた影に気づかずに、ある瞬間。
(チラシより)どこからともなく届く光は、自然から成されたものではないことは解っていた。いつかの誰かが、誰かへ向けて発した光だった。ある人は、その光を見て見ぬふりをした。ある人は、その光自体を無いことにしようとした。しかしわたしには届いていた。届いたからにはわたしからも光を送りたくなった。届く光に微かな瞬きを感じた。光が在るということは、その傍には誰かがいるはず。光の合図は確実にここまで届いている。