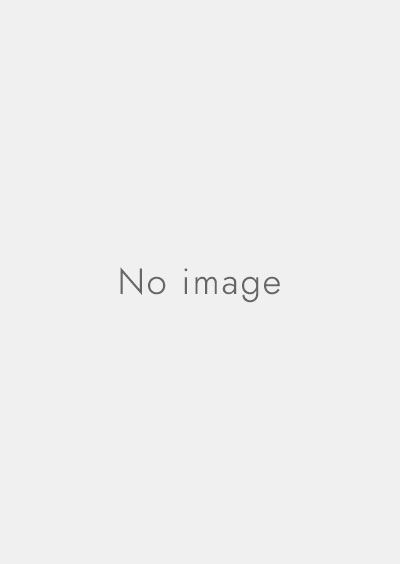【作品ノート】2019年頃に感じていた、何だか静かで人類が世界に退屈したような絶望感がある。それが前回の横浜ダンスコレクションで上演した「サイクロン・クロニクル」が纏っていた空気感でもあった。
2020年2月以降、その絶望感が一気に沸点に達して吹きこぼれ、今も尚ぐらぐらと煮立っている。そして、その鍋の中に生成されているのはデカダン的な新たな終末感である。
その中で新しく作品を作ることになり、浮かび上がってきた題材がいくつかあった。一つ目は、人生に絶望し自らの魂と引き換えに悪魔と契約する物語「ファウスト」である。
この物語は中世ヨーロッパに流行した錬金術師ファウスト(またはフォースタス)の伝説が基になっており、人形劇や寓話、小説として時代や作者ごとに設定や結末を変えて語られている。二つ目は、同じく中世ヨーロッパで、ペストの猛威の中で生まれたとされる死生観であり今日では芸術の一つの形式にもなっている「ダンス・マカブル」=「死の舞踏」である。
死の擬人化としての骸骨、特に教皇、子供、作業員など様々な階級の人々が身分の見分けのつかない骸骨となって列をなして描かれるのが特徴で、生前の貧富や権力も死の前には無力であり、死後は等しく無に統合されてしまうというメッセージを持っている。
三つ目は、江戸末期の日本で、時代の転換期を前にお札が空から降ってくるという神威的な出来事をきっかけに人々が熱狂的に集団で町々を踊り歩いた「ええじゃないか」四つ目は、近未来的な世界で、破壊衝動、快楽、自由を求める若者たちと全体主義的な社会との歪みを描いた「時計じかけのオレンジ」(今作では映画版を参照)
こうしてみると、なんだか狂気じみた自己崩壊や集団ヒステリーのようなものをコレクションしているようだが、私がこれらに共通して見ているのは「孤独」である。
私は今の世で、人々がまるでそれぞれのパラレルワールドを生きているかのように思うことがある。どの数字を信じるのか、何を身に付けているのか、どんな知らせを待っているのか。それ一つで、見える世界が以前とはあまりにも違うのだ。そして、それは他人と共有することがとても難しい。現実を見れば見るほど、自分だけが地獄にいるような気がしてくる。
「人間が地獄と呼ぶ場所はどこにある」と悪魔メフィストフェレスに尋ねたファウストに、「天国でない場所は全て地獄となる」とメフィストが答えたことを思い出す。
パラレルワールドの孤独は限界がくる。もしかしたらその到達点で起こるバグが集団ヒステリーや恒常性バイアスを引き起こすのではないだろうか、と私は仮定する。
そんな世界の中で、私にとっての「悪魔」とは、善悪の二項対立の中のマスコットキャラクターなどではなく、自分にしか見えていないはずの地獄を唯一共有できる友である。
それは時に黒い犬の姿をしていたり、暴力やセックスであったり、ダンスだったりするのだ。
そういえば「ダンス・マカブル」という言葉には、葬儀などの場で突発的に発生した集団での人々の踊り、その様相も含まれている。ペスト大流行の中で特効薬もなく、埋葬も葬儀も間に合わない。ついには祈りすら役に立たなくなってしまった中で、人々は半狂乱になり倒れるまで踊った。死への恐怖からか、生への執着か、その中で「メメント・モリ」=「死を想え」という言葉も広まったという。死にゆく人々の中で、見捨てられていく人々の中で、自分の順番を待つ中で、死を想うため、そして自分自身を救うために踊った彼らの姿を、私は自分の中にも発見する。
この狭い鍋に沸え立った絶望の中で、今、ダンスを作るということ、踊るということ。
私たちはそれぞれのパラレルワールドを、孤独を、今ここに大切に持ち寄って来ている。
私たちに死ぬのが怖いと言わせてほしい。
これが、今、私が言いたいことである。
それはきっと、陽気な人々を不安にさせる、暗い、弱い、小声になる、自分だけの、恥ずかしいものだろう。それはきっと、悪夢を見て泣きじゃくる子供のような、思いがけず触れてしまった猫の腹のような、やわらかい、慎ましい、あたたかいものだろう。
そして、それをそのままにしておくために、この時代に目撃されるために、今この作品を上演したい。
この鍋の中の全ての人たちへ。私の地獄からデビルダンスを、
愛をこめて!
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
1913年に創建された倉庫をリノベーションした文化施設。コンセプトは「芸術文化の創造発信」と「賑わいの創出」。コンテンポラリーダンスやアートを柱に、新進アーティストを世界に発信している。フレキシブルな機能を持つホールとギャラリースペースを有し、ダンス等舞台芸術公演や展覧会、屋外広場でのイベント等を通じて横浜の文化と観光のハブ機能を担う。
AFTER RUSTは「錆の次には何が起こるのか?」という疑問をベースとしたソロ作品。人間の身体と精神両面での錆に着目し、物質が錆びた後には何が起こるのかを探求した作品です。クリエーションを行った昨年はちょうど30歳を迎えた節目の年でした。この数年ダンサーとしての仕事よりも振付や教える仕事が増え自分自身に集中できる時間が減り、徐々に体が錆びて劣化していくような感覚を感じていました。この錆と向き合い
作品ノート:日々、悶絶しております。 いえ、悶絶のてまえ一歩でもんもんと。 しかし、その一味 意外と美味しいかも。 3000円くらいの自己肯定、味わっていってください。
私たちはカラダのことを知っているようで私たちはカラダのことをまだ知っていないあなたの中にある私私の中にあるあなた私はまだ私を見たことがないあなたを通して私を見る私を通してあなたは見る凹凸世界は変わり続け身体は変わり続け凹凸私たちの最後の破片を探す旅は続く私たちのカラダはまだ不完全だから身体を所有した時から私たちの旅は始まった
[作品ノート]He-for there could be no doubt of his sex, though the fashion of the time did something to disguise it… ("Orlando", Virginia Woolf)(※彼-性別はまず疑う必要のない男、たとえ当時のファッションが彼の外見を変えることができるであろうとも…)自分が例えば誰か