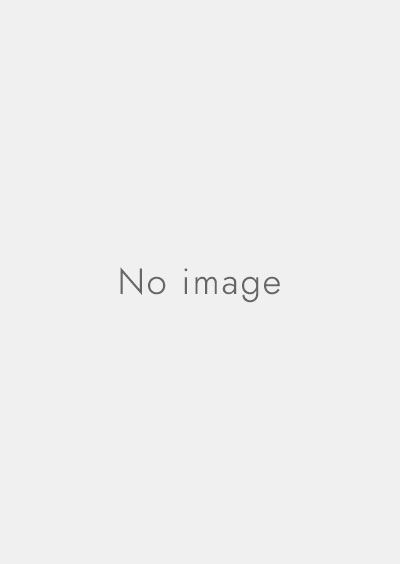病気が流行して四年。流行り廃りなんて四年もあれば、ほとんどなんでも廃れるもんだけど、病気は未だ廃れない。特に酷かった二年目の冬。一緒に暮らしている人がいることだけが救い。ある日、一緒に暮らしている人が「これからは糸電話で話そう」と言い出した。同じ家に住んでいるのに私たちの距離はどんどん開いていった。私は不満だった。私は不安だった。ここ数年で溜まりに溜まった、鬱憤の話。
劇作家や映像作家、俳優、ダンサー、写真家など多様な作家が集まり、それぞれ互いの創作領域に踏み込んで演劇をつくる集団。旗揚げ公演『ミルユメコリオ』でせんだい短編戯曲賞を最年少受賞。文化庁文化交流事業として『56db』を製作、二ヶ国五都市で上演など、「今まで演劇に触れたことがない人にきてもらう/演劇が行けなかったところへいく」ことを目的に、国内外や劇場内外を問わず挑戦的な作品を発表し続けている。
海に分断され、八つの陸地に分かれた“いつかの日本”。最も小さな島に住んでいた民族“バンチ”は労働力として本土へ連れてこられ、割り当てられた小さな居住区に住んでいた。それから数十年が経ち差別も偏見も薄れ、その存在自体が人々の記憶から消え始めた頃、バンチは絶滅しかかっていた。最後の子供たちは、バンチ色の眼をカラーコンタクトで隠して、今日も居住区の外を歩く。“自分の居場所はここじゃない”と感じる人たちの
地下鉄のホームで電車を待っていた裁判官・徳丸 透 (トクマルトオル) は、15年前に捨てた息子・春 (シュン) が向かいのホームに立っているのをみつける。春の眼が見えないことに気が付いた透は、赤の他人を装い近づき、「一緒に住まないか」と誘う。一度破綻した親子の、二人暮らしが再びはじまる────。
幽霊達の駅・京都駅地下鉄清水線。その十二番出口にあるコインロッカーのことを、兄弟は『母』と呼んでいる。二人は十八年前、このロッカーに捨てられていた赤ん坊だった。閉鎖していく幽霊の駅を舞台に、生きる者と死んだ者の「駄々」を描く群像劇。
パンチドランカーとなり引退したボクサー・無口は、寝たきりの 人々の家を巡る「殴られ屋」を生業にしていた。ある日寝たきりの女・わたげに殴られたことをきっかけに、無口は痛みを感じなくなってしまう。同じ街のコールセンターでは通販サイトのクレーム処理部門で働く青年・寝々が、山から降りてきた熊を銃で 仕留めることを夢見ていた。バラバラだった彼らの物語は「動物園の熊を安楽死させる」という情報が流れたことで、急