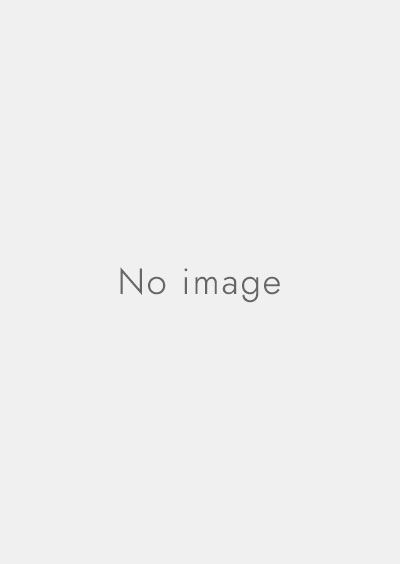コンセプト:『星の王子様』×『禅』。映像を駆使した空間演出と会場のデザインを活かした演出。音楽家とのコラボによる新たな観劇体験の提供。内容:水槽を旅する不思議な魚と肉親の死と事故によって塞ぎ込んだ青年との出会いと別れを描く物語。物語の中心にあるモチーフとして星の王子様と禅をとりあつかい、世界は自分自身が何を思うかによって変えることができることに気づき、最後には青年が外へ踏み出す話となっている。
宮崎の小さな電気工事会社に勤める町村(まちむら)は、40歳を過ぎても独身でボロアパートに一人暮らし。趣味と言えば酒くらいで、ほぼ毎晩記憶を無くすほどに酔い潰れている。ある朝、お決まりの二日酔いで目覚めると、洋服に血がついていた。しかしそれがなんの血なのか分からない。行きつけのスナック「シャンドレ」に行ったことだけは間違いないが、それ以外の記憶がまるでない。果たしてこれは……。町村と彼に関わる男たち
きのう落とし忘れたPCがまぶたを刺す。肩はぼんやりとしたひかりに囲まれて、ようやく輪郭線を生んでいる。部屋にのこるけんかの痕跡が、いよいよ目の前にあらわれる。日はのぼるらしい。俺はあるはずのない水平線を、窓に感じている。それを眺めるほか、できることはあるのだろうか?第13回せんがわ劇場演劇コンクール参加・オーディエンス賞受賞作品。恋人と別れた人の部屋に、深夜友人が訪ねてくる。
せんがわ劇場の客席と舞台との距離や空気の層に、霧の立ち込めるような鬱蒼さを感じました。さらに、強固な空間には根を張ったような印象を。これまでは、ぎゅうぎゅうとした生活圏内で人と距離を取ること、取らないこと、あるいは取れないことを多く考えてきたように思います。今作のモチーフは森です。他者だけではない広い外部の世界に、どのように自分を置くのでしょう。
20代後半を迎える朝美、かのこ、ゆず、美緒は元高校演劇部であったことを共通点に、友人関係にある。ある日、顧問の先生の訃報と残された草稿が発見される。「わたしはことばそれ自体になりたかった」「欲望は見えなくされているだけだ」と書かれたそれは、完成された物語ではなく、未完成の言葉の集合体だった。4人は残された言葉を「聞く」ことからはじめようとする。