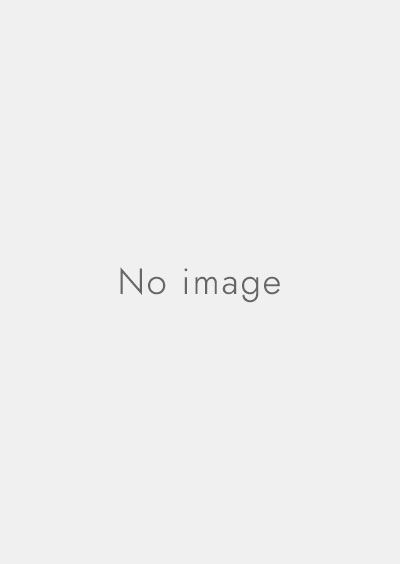三好十郎が1950年に発表した大戦前後の日本を舞台にした『殺意(ストリップショウ)』。
ナイトクラブのステージで、引退ショウを行うソロダンサー緑川美沙。南の小さな城下町に生まれ、愛国運動、敗戦を経て東京でダンサーになるまでの半生に秘められた激情を、自身最後のステージで語り出す。
河井朗が主宰、演出する実演芸術を制作するカンパニー。
ここ近年は年齢職業問わずインタヴューを継続的に行い、それをコラージュしたものをテキストとして扱い上演を行う。
そのほかにも既成戯曲、小説などのテキストを使用して現代と過去に存在するモラルと、取材した当事者たちの真実と事実を織り交ぜ、実際にある現実を再構築することを目指す。
1906年ダブリン生まれのサミュエル・ベケットは、第二次世界大戦を経験しました。翻訳者・岡室美奈子氏は、彼にとって「不条理」とは難解な思想ではなく、きわめてリアルな世界の見え方だったと語ります。『エンドゲーム』の舞台は核戦争後のシェルターとも言われ、灰色の終焉の世界が描かれます。不条理とは社会の理屈に合わないこと。私たちの日常にもそれは潜んでいます。あなたは、どんな不条理と共に生きていますか?
ルサンチカが、これまで不特定多数に「仕事」についてインタビューし制作した舞台作品のリクリエイション。斉藤綾子を出演に招き、彼女の持つ肉体を頼りに「存在」と向き合っていく。ダンサーである彼女は踊ることが働くことと繋がっている。どこからが公のための踊りで、どこからが自分のための踊りなのか。そもそもそのような境界は存在しているのか。ダンサーの彼女と対話を用いて彼女と彼女自身と向き合っていく。
2025年の私たちは、性別に関係なく「俳優」と呼ぶようになりました。それは、よりよく生きるために積み重ねられてきた努力の一つです。『楽屋』には四人の「女優」が登場します。1977年当時の「女優」が背負っていた意味を私たちはもう理解できないかもしれない。けれど、その苦しみを「人間」のものとして受け取ることはできるかもしれません。そのような1つの新しい挑戦として『楽屋』を上演します。
本作は不特定多数の人々へ行ったインタビューを用い、社会学者スタッズ・ターケルの本を原案としたものとなります。「GOOD WAR」には、私たちが「戦争」と聞いて想像する争いと、社会に実際に存在する争いの両方が含まれています。争いに勝った人、争うことをやめた人、これから争う人、争いから逃げる人が剣闘士として登場し、「よい争い」と「わるい争い」の区別がないことを実感しながらも、自分の生活のために争いを行