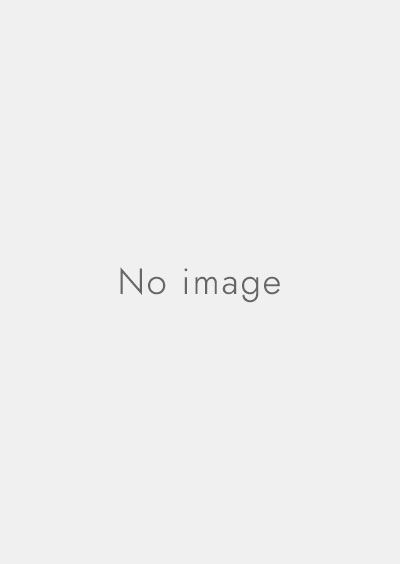遠藤は1970年代に渡欧し、マックス・ラインハルトセミナーに学び、以来長年ドイツと日本の二拠点で活動している。本作は東北大震災直後の日本に寄せる思いを作品化した。自然災害としての地震、人災としての原発事故、そして人々の悲しみと再生への希望が語られる。
2012年10月、ハノーファーのTheaterwerkstattで初演。
遠藤は1970年に渡独、ウィーンのマックスラインハルト演劇学校演出科で学び、ドイツで俳優、演出家、振付家として活動。80年にダンスを始め、89年の大野一雄との出会いを機に舞踏の道に進む。92年、遠藤ガブリエルとゲッティンゲンに「舞踏センターMAMU」を設立、舞踏フェスティバル「MAMU Butoh & Jazz」を始める。舞踏センターMAMUは遠藤によるワークショップ等が行われ、舞踏関連の映像と本を多く所蔵、舞踏を学ぶために世界中から多くが訪れている。
ゲッティンゲンで開催された第一回マム・フェスティバルの一環として行われた。フェスティバルは一貫して、「舞踏とフリージャズ」をテーマとして例年開催、舞踏家、ジャズミュージシャンを招聘した。本作は、遠藤と高瀬、沖による即興的なセッション。
遠藤が20数名のダンサー達と作り上げた作品。学校校長であった遠藤の父親が、焼けた校舎の跡に芽吹いたメタセコイアに勇気づけられ、絶望の淵から学校の再興を決意した体験から、自然が人間にとって如何に大切かをテーマに作品制作に取り組んだ。
遠藤が終生のテーマとする「死」を探求した作品。死によって肉体と魂が遊離し、魂は目に見えないなにかとして私達の周りに漂っている。遠藤は「幽霊」を演じることで、舞踊家のリアルな身体とともにある「幻」のような何かを表現している。2019年パラチ (ブラジル) の文化センター、セスキ・シーロ (SESC Silo) で初演。