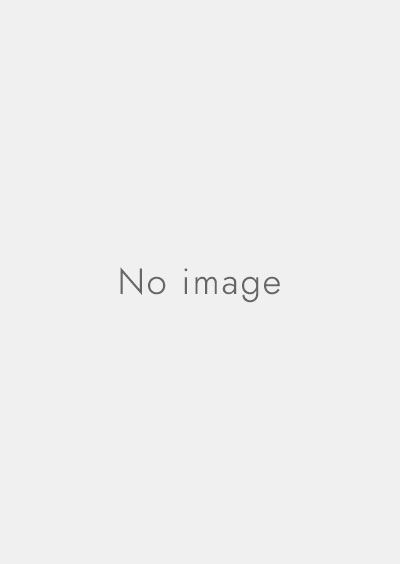日本の舞踊では、舞・振・踊りと三本の柱にたとえられる分極がある。「ふり」は、その振を本来の意味のダイナミズムに開放したいものとしてつけられた公演名。服部公一作曲の本公演オリジナル曲を含んだ楽曲を手塚幸紀指揮のオルケストル・ソノーㇽ(録音素材)、美術を当時新進気鋭のジェームス・川田が担当。ダンサーは女性10名、男性12名で、衣装はシンプルなレオタード、タイツであった。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
前衛的な踊りで知られた津田信敏に師事した若松美黄と津田郁子が設立した「若松美黄・津田郁子自由ダンスカンパニー」が、1969年の「回復路線」を皮切りに2009年の「笑いの箱」まで毎年42回連続して行った公演。そのうち「ふり」「村へ帰る」「暗黒から光へ」「ジーキル博士とハイド氏の寓話」が文化庁芸術祭優秀賞を受賞している。
博士の生命に対する執着から産み出された不完全な生命体の物語。愛する人の死を受け止められない。愛する人と過ごす幸せな未来を願う人々。生から死、死から生の輪廻の輪から外され壊れていく一人の男。命と云う神秘に見せられ、ただ全てを知りたかった一人の博士。恐ろしく悲しい物語だ。
男は演出家。家では夫、父、息子。オイディプス演出中に発病し、入院する。癌と疑い、医師、家族、友人に真実を教えるよう迫る。嘘と隠蔽の中、彼はオイディプスと自らの行動を比較。不治と察しつつ、家族の思い遣りを傷つけまいとする。オイディプスに重ね合わせ死を見据えるうち、日本の風土や人情を容認する気持ちになる。クリスマス、友人と家族と共に、そのひと時を心から楽しもうとする。外にはすべての汚れを払う雪が舞う。
映画監督ヴィーネによって有名になった「カリガリ博士の箱」をバレエ化した。物語は精神を病んだ男の妄想の話。人体実験をする博士。実験の為に誘拐されてしまう女性。女性を助けようと乗り込んだが捕らえられてしまう男性。実験によって狂わされていく女性と精神を犯されていく男性。最後は病んだ男性が自分は博士だと思い込み博士と女性を殺し、自身も炎にまみれるところで終わる。何処まで事実で何処からが妄想なのか?
ニューヨークのバレエ教師クビノ氏は、紙を丸めて空中にほおり投げ、「これがバレエだ」と言った。自然の落下そのもののことを。レッスン帰りにオペラハウスの噴水前で踊ったものだ。笛を吹くのは仕事も家もないその日暮らしの自然食主義者。彼の生活が自然の生活ならば、やはり重すぎる。自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらぐ。キドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。それは自然か、不自然か。