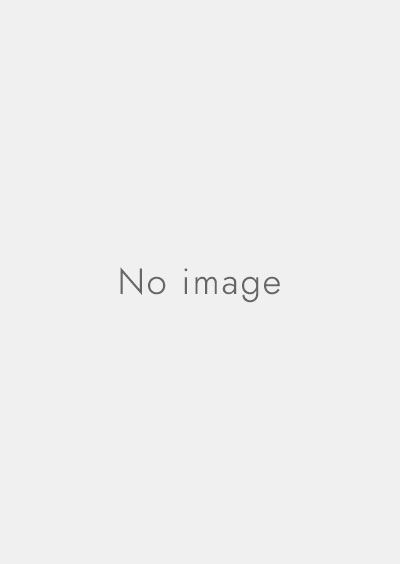おねしょに悩むおんなのこは、飼い猫のにゃあにゃあちゃんから聞いた古い言い伝えを叶えるため、夜の森へ出掛けて行きます。おかあさんも子どものころに出かけた森には、たくさんの動物たちや不思議な生き物、妖精たちが住んでいました。森で出会った狩人に案内されて森の奥へ進むおんなのこ。やがて辿りついた古いおうち。となりの森と戦争が始まろうとする中、おんなのこが古いおうちで見たのは……。
(パンフレットより)なんかわからないけど、ここ数年、たえまなく、この作品と向き合ってきた気がするけれど、なんでこの作業を選んできたかというのは、自分にとっても、まったくに不思議なことだ。でもどうしてだろう、なにがしたい?と問われると、あっこのはなし。と答えてきたのだった。それはなんでだろう、あんまりかんがえて答えていないようにもおもうけれど、でも直感として、この作業をしていなくてはいけない、と自分
(パンフレットより)一月に書いた文章を眺めている。あれから、なにを経て。どんな音を聞いて、どんな光景を目に映して。どんな時間を過ごしてここまで巡り、辿りついただろう。想像もしていなかったようなことは、やはり起こる。それに伴って、線なんか引かれていなかったところに線は引かれていく。内側と外側があるのだと知る。部屋のなかで窓より外の世界を想像するのがこんなにも不安なことだった、だなんて。しかし、やはり
(パンフレットより)じっさいにその作業をするのにかかる時間をつなぎあわせて、どういうヒカリを暗闇のなかにいれて、物事を、風景をみつめていたか、ということをあらためて取り組んでみてかんがえた。おそらく、みえているものすべてが本物ではないことは、幼いころからわかっていた。では、本物はどこにあるのだろうか。右眼を塞いで、左眼だけで遠くのほうをみつめながら、そんなことを想っていた。ぼやけた画面のなかに、本
(パンフレットより)生まれてきた奇跡のさきへつづく旅路。それは森であり、夜である。ただ歩いていくのは困難で、立ちはだかるものをまえに立ちつくす。見たくないもの、聞きたくないものに触れてしまう瞬間が、やがて誰しもに訪れる。ときに、どうしてこんな世界に生まれてきてしまったのだろう、とおもうかもしれない。けれども、生まれてこなければ出会えなかった。たまには立ちどまって、来た道をふりかえってくれていい。思
(パンフレットより)三年前にこの作品は一度、故郷の北海道伊達市で、終わりを迎えたはずだった。だけれどまたこうして取り組んでいるのは、この三年間で家という生命体そのものが、現在という時間のなかでどう在ればよいのか、という問題が自分のなかで、まるで変わってしまって、膨らみつづけていたからだろう。現在という時間は想像できているだろうか。あのころの食卓のこと。ひとりひとりの表情を。家という生命体の内臓は、
(パンフレットより)おもえば、いつだって夜だった、たとえ朝がやってきたとしても、それは時間がそうさせているだけであって、夜であることに変わりはなかった。たまに笑ったのだとしても、それは夜に笑ったにすぎない。そうだ、夜だった、と我にかえって表情を失くすのだった。さいきん、ますます夜は暗闇を増すばかり、どうしたらこの暗闇から抜けることができるだろうか、なんてかんがえるだけ無駄かもしれない、もはや。だけ