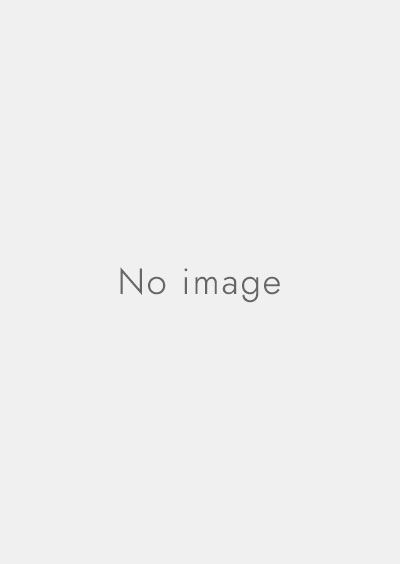(パンフレットより)
おもえば、いつだって夜だった、たとえ朝がやってきたとしても、
それは時間がそうさせているだけであって、
夜であることに変わりはなかった。
たまに笑ったのだとしても、それは夜に笑ったにすぎない。
そうだ、夜だった、と我にかえって表情を失くすのだった。
さいきん、ますます夜は暗闇を増すばかり、
どうしたらこの暗闇から抜けることができるだろうか、
なんてかんがえるだけ無駄かもしれない、もはや。
だけれど、ひとは、どういうわけか、
夜明けを目指す、ということも知っているから、
だからなのだろう、ものを書くようになってから、ずっと、夜のこと。
つまり同時に、夜明けのことを、夢見るようにして、描いてきた。
あの静かな水辺のほとりにて、止まってしまっている時間がある。
駅にて、いまでも誰かを待っているひとがいる。
きょうも、この町から、この世界から、ひとがいなくなった。
祈っているのだとおもう、変わってほしい、と。
きのうときょうがちがったように、では、あしたは?
やがて訪れる、ほんとうの朝を待っている。
無駄かもしれないし、完璧なんてあり得ないのもわかっている。
それでも待っている。死ぬまで待っている。
だから描いている、夜のこと。朝のこと。
果てるまで、描くのだとおもう。
2017.7.6 藤田貴大
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
藤田貴大が全作品の脚本と演出を務める演劇団体として2007年設立。2012年よりオリジナルの演劇作品と並行して、他ジャンルの作家との共作を発表。あらゆる形で作品を発表し、演劇界のみならず様々なジャンルの作家や観客より高い注目を受けている。
(パンフレットより)「四月の始まりと、異邦人が終わったあとの、あ、ストレンジャー」三月も、もう終わります、(つまりこの文章は、三月も、もう終わるって頃、ぼおんと、磨りガラスの窓の向こう、朝日が登り始めた、っていうのを、布団の中で眺めながら、書いています、)もう少しで、四月が始まります、『あ、ストレンジャー』は、四月の始まりに始まって、四月の始まりに終わります、(布団を出ることにします、机の上で林檎
(パンフレットより)頭がキリキリする、はあ、八月、も、もう中間付近、僕、相変わらず、作品、つくっている、そりゃあ、汗だくになりながら、つくりまくっている、つくって、疲れて、今日もアパート帰る、帰って、部屋で、腐りきっている、ちょっと腐って、復活して、また、頭の中で、また作品、つくる、翌朝、作品つくりに、家を出る、駆け足、で、稽古場、に、向かう、そんなループの中、に、僕はいて、つくるつくる、を、繰り
マームと誰かさん・さんにんめ
マームとジプシーを率いる藤田貴大が第56回岸田戯曲賞を受賞した直後、他ジャンルの作家との共作シリーズ「マームと誰かさん」を企画し、小さなギャラリーにて作品を発表。このシリーズはその後マームとジプシーに大きな影響を与えました。その第三弾は漫画家・今日マチ子さんとのコラボレーション。
(チラシより)どこからともなく届く光は、自然から成されたものではないことは解っていた。いつかの誰かが、誰かへ向けて発した光だった。ある人は、その光を見て見ぬふりをした。ある人は、その光自体を無いことにしようとした。しかしわたしには届いていた。届いたからにはわたしからも光を送りたくなった。届く光に微かな瞬きを感じた。光が在るということは、その傍には誰かがいるはず。光の合図は確実にここまで届いている。