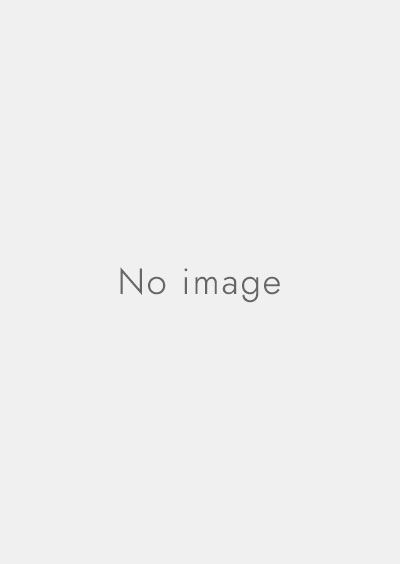白石加代子「百物語」第十七夜
白石加代子「百物語」第十七夜
演出の鴨下さんが病気になられて、「百物語」が一時中断し、久しぶりの岩波ホールでの公演である。
鴨下さんは「百物語」のコンセプトについて次のように語っている。
「捨てるだけのものは全部捨てた、ヴィジュアル面もそうですが、第一覚えなくていいわけでしょ、だから記憶力も捨てた。相手役も捨てた。演劇の要素をどんどん捨てていった。
だから僕は、演劇にはなりっこないと思っていた。ところが、そうやってどんどん捨てていっても、それでも演劇になる。
それが最大の発見です。音楽、美術、まあ照明はちょっとあるけれども、相手役はいない、覚えなくていい、台本を見るわけですからどこを見るというような目線も決められない。
表情だってそんなに作れない。動きだって作れない。でも、動くし、目線はあるし、相手役もいるように見えるし、覚えないでやってるようには見えない。ないものづくし、ところが全部条件を捨てても演劇は残るんだね。どうしてなんだろう。それが一番の発見でした。こんな最小限度の演劇ってないんですよ。しかし、それが最もシアトリカルでドラマティックなアートになっている。それが僕は一番不思議だと思う。
もう一つはね、「百物語」をやるまでは、白石さんという女優さんが、こんなにユーモアがあって、膨らみがあって、セクシュアルなところがあって、という人だと思わなかったのね。そういういろんな要素がこの人の中に内在しているというのは知らなかった。
実際に「百物語」をやってみて、ああ、この人の中にこんなにたくさんのものがあるんだと分かったのが、二つ目の発見ですね。その芽を伸ばしていけば、「百物語」って大丈夫なんだという自信を、第一夜から持てた。
三番目は、日本語のいいものをやりたい、というのがテーマとしてありましたから、日本語としてふくらみのあるいろんなものが出来てきたというのが、やはり成果のひとつでしょうね。日本語としてどうか、ということが稽古でもいちばんうるさく言っている部分なんです。
日本語を音声に出して読むということは、どういうことなのか。どういうことが日本語を読むということなのか、というのがやっている間に僕らが覚えたことだろうと思います。
この三つが一番の成果なんじゃないでしょうか」
浅田作品はたまたま読んでいて、何だこれは怪談じゃないかと強引にレパートリーにする。「うらぼんえ」があまりにも好評だったので、2匹目のどじょうを狙って、「鉄道員」を取り上げる。しかし、「鉄道員」が二匹目とはあまりにも贅沢な話である。「昆虫図」はショートショートの名作。毒がいっぱい詰まった話だが、久生十蘭の言葉は豪華絢爛で密度がある。こういう文体に出会った時の白石加代子は俄然生き生きとしてくる。「赤い鼻緒の下駄」は、台本の見返しの部分が赤であり、舞台はそれをうまく小道具として使っている。時々、鴨下演出はそういった奥の手を見せる。赤い鼻緒の下駄が揃えられた、少女の眠る部屋に入っていく場面が印象的だった。
(百物語シリーズ総集編パンフレットより転載)
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
1990年設立。主な作品に、大竹しのぶ「奇跡の人」、古田新太・生瀬勝久「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」、西城秀樹・鳳蘭・市村正親「ラヴ」、天海祐希「ピエタ」などがあげられる。(メジャーリーグHPより)
輝かしい命を持った13歳が自らの手でその命を絶った。誰もがその事件の当事者である。空を飛ぶ翼を、銃弾で撃ち抜かれ、二度と飛べなくなったノガモとは、夢見る力を、現実という銃弾で粉々にされしまった人間のことである。それでも彼らは生き続ける。人間を見に来て欲しい。人間ほど面白いものはないのだから。
白石加代子「百物語」アンコール公演
明治から現代の日本の作家の小説を中心に、「怖い話」「不思議な話」を、白石加代子が立体的な語りと動きで演じる人気シリーズ白石加代子「百物語」のアンコール公演。恐怖とユーモアとが絶妙に味付けされた人情怪談、宮部みゆき作「小袖の手」と、一冊の本に挟まれた時空を超える栞をめぐる不思議な恋の怪談話、朱川湊人作「栞の恋」の2本立て上演。
不思議な一座が幻のように現われ、幻のように去っていく。何もない空間から始まり、何もない空間で終わる。しかしその舞台は見る人に強烈な印象を残した。女優がハムレットやホレイショーを演じ、ガートルードやオフィーリアを男優が演じた。しかしそれが何の違和感も残さず、よりくっきりと「ハムレット」の世界を映し出し、より明確にドラマの構造を浮き彫りにした。お芝居好きの人に是非観てほしいと思います。観たこともない「
マクベスは夢を見る。栄光と権威、王冠の夢を。しかしそれは引き返せない悪夢だった。そしてその王冠に手をかけたときから、坂道を転がるように、破滅への道を一直線に突き進む。