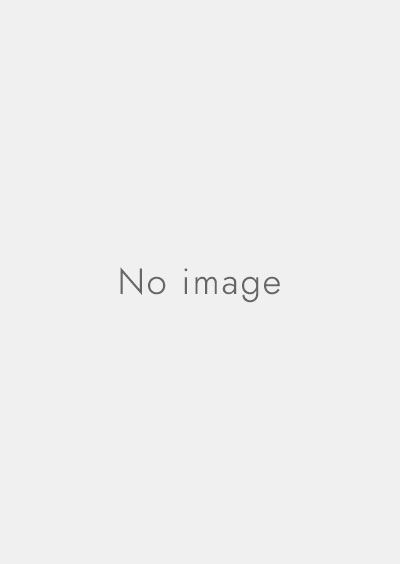(パンフレットより)
頭がキリキリする、はあ、八月、も、もう中間付近、僕、相変わらず、作品、つくっている、そりゃあ、汗だくになりながら、つくりまくっている、つくって、疲れて、今日もアパート帰る、帰って、部屋で、腐りきっている、ちょっと腐って、復活して、また、頭の中で、また作品、つくる、翌朝、作品つくりに、家を出る、駆け足、で、稽古場、に、向かう、そんなループの中、に、僕はいて、つくるつくる、を、繰り返して、いる。頭、キリキリさせる元凶、は、この作品、塩ふる世界。
この作品、難解。実に、難解。最上級に、わけのわからん、崖の上の際も際で、強風に当てられて、つくっている心地する、マームとジプシー、2011年、夏、の三部作、『かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。』の、終着点、これにて、三部作は終わりを迎えるのである、と同時に、マームとジプシーの2011年、後期、は、ここから始まる。僕が、この作品を始点と構えて、ここから先を、展望しているのは、明らかである、宇宙戦艦ヤマトで例えて言うならば、波動砲を打つ、一歩手前みたいなもんである、いや、もう波動砲、打つかもだから、それこそ、構えて見ていてほしいくらいにして、兎にも角にも、僕は、それくらい、この作品に入れ込んで、作り込んでる、っていう、手っ取り早く言うならば、そういうことだ。そういうことだ。
そう、それで、今回、この作品を通して取り組んでいること、とは、こういうことだ。
役者さんの身体が、どう、物語や感情を、recovery(回収)していくか、そして、そのrecovery(取り戻し)したモノを、どう、recreate(改造する)し、空間全体にreturn(返還)していくか。
つまり、僕の頑固な書き物、及び、記憶、をどう、役者さんの身体は、言動と行動を用いて、変換して、僕に、或いは、空間全体に、どう、返してくれるのか。
その作業を、繰り返し、揺さぶることによって、
文字は文字化けして、舞台上に転がりながら存在する言葉たちは、
誰の所有物でもなくなるんじゃないか、
或いは、誰もが等しく共有できる、この場所・土地で、今まさに生まれた、産物・資源(resource)になるのではないか。
そして、それを、空間にいる誰もが、手にとり、口に入れて、咀嚼しだす、という、反応(reaction)をしていくのではないか。つまりつまり、空間にいる誰もが、反応する人(reactor)となるのではないか。
こういった“re”の連鎖を考えて、つくっている、塩ふる世界。
これ、まるで食物連鎖、そうそう、この三部作は、食べ物に纏わる、作品群だったんだよなぁ。
僕は、繰り返す、しつこく、これからも繰り返していく、繰り返し、演劇を稼働させていく、記憶も感情も繰り返し、言動も行動も繰り返していく、繰り返し繰り返し、これからも作品つくっていく、頭、キリキリさせながら、際も際で、繰り返していく。
もう、僕には、それが演劇表現、そのものに思えてしょうがないのである。
2011.8.8 藤田貴大
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
藤田貴大が全作品の脚本と演出を務める演劇団体として2007年設立。2012年よりオリジナルの演劇作品と並行して、他ジャンルの作家との共作を発表。あらゆる形で作品を発表し、演劇界のみならず様々なジャンルの作家や観客より高い注目を受けている。
(パンフレットより)「マームとジプシー的、真夜中の考察と、季節の移り変わりとは無関係に、移行していく真夜中のイメージ。で、朝は訪れるのか、どうか、っていう。」というわけで、今回は、真夜中、という時間にだけに取り組んだ、でもしかし、果たして、この真夜中に、朝は訪れるのか。今夜もまた、夜が明けないまま、朝を迎えることになるのだろうか。僕は、これからも、終わることのない真夜中、を、行くのだろうか。また、
マームとジプシーが小説家・川上未映子とタッグを組み、川上の書き下ろしの詩を含む6作品を俳優・青柳いづみの一人芝居として上演。2014年3月から約2ヶ月をかけて全国8都市にて巡演。
マームと誰かさん・ふたりめ
マームとジプシーを率いる藤田貴大が第56回岸田戯曲賞を受賞した直後、他ジャンルの作家との共作シリーズ「マームと誰かさん」を企画し、小さなギャラリーにて作品を発表。このシリーズはその後マームとジプシーに大きな影響を与えました。その第二弾は演出家・飴屋法水さんとのコラボレーション。
(パンフレットより)「ほろほろ」今まで、たくさんの人と別れてきて、きっと、これからも、別れるだろうと、そう思って、この作品は出発した。記憶を巡ってみても、思い出すのは、断片的な、しかも、ぼやけて色褪せた、曖昧な風景で、そんな、脳内の、それに、フォーカスを合わせ、シャッタースピードも最速に上げて、記憶の一瞬を、捉えようと試みた。それが、どれだけビビットに映ったか、もしくは、もう、記憶は、ぼやけたまま