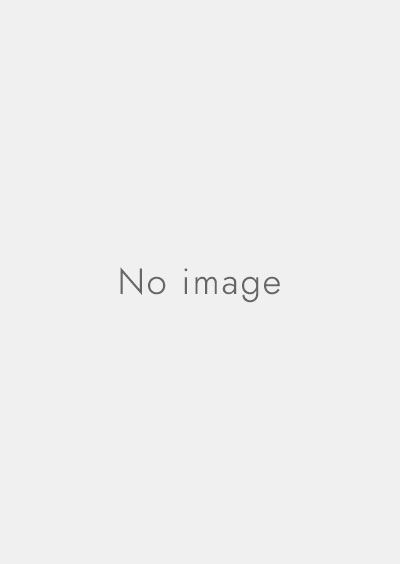魯迅は、いまさら言うまでもなく、アジアを代表する世界的文学者の一人です。たとえば、1927(昭和2)年、ノーベル賞選考委員会は上海へ特使を送ってきました。その年の文学賞を受けてくれるかどうか、魯迅の胸中を打診にきたのです。さまざまな不幸な理由から、魯迅はこれを断りますが、とにかく彼はそれくらい注目されていたのです。
魯迅は、それから10年とは生きておりませんでしたが、ここに不思議なのは、彼の臨終に立ち合ったのが、彼の妻と弟のほかは、みんな日本人だったという事実です。
帝国日本を心底憎みながら、しかし日本人を心から愛した魯迅。これは魯迅とその妻と、彼の臨終に立ち合った4人の日本人のちょっと滑稽な、しかしなかなか感動的な物語です。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
私たちは、人を泣かせたり、笑わせたりしている会社です。
座付作者井上ひさしに関係する作品のみを専門に制作、上演しています。
1983年1月に創立し、84年4月『頭痛肩こり樋口一葉』公演で旗揚げ。
以降、新作、再演、こまつ座旗揚げ以前の井上作品も織り交ぜて、出演者・スタッフとも作品ごとに依頼し、その作品だけの一座を組むプロデュースシステムをとり、年平均4~6作品(200~250ステージ)を上演し続けています。
井上ひさしが『小林一茶』に続き“俳諧師”を題材に描いた今作は、40年にわたるこの芭蕉の俳人としての人生を、一人語りを中心に富士三十六景になぞらえて全三十六景で描きます。ほぼ一人芝居とは云え、めまぐるしい舞台転換、様々な景を支える黒子とも、芭蕉は絶妙な会話を重ね、その人生を彩り豊かにあぶりだします。苦悩する芭蕉がやがて到達した視点を描くだけではなく、人生の豊かさやその可能性の大きさを伝えています。
―これは井上ひさしが愛してやまない日本語に、不思議でかわいらしく、輝くような生命を与えてくれた、ある岩手花巻人の評伝劇―詩人にして童話作家、宗教家で音楽家、科学者で農業技師、土壌改良家で造園技師、教師で社会運動家。しなやかで堅固な信念を持ち、夭逝した宮沢賢治。「世界ぜんたいが幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」そう信じた宮沢賢治が夢見たイーハトーボは果てしなく遠かった。
嘉永(1853)六年師走のある晩、我が身の先行きを悲観して両国橋から身を投げようとした狂言作者の二世河竹新七。ところが奇妙な行き掛かりで、無我夢中の新七が飛び込んだのは大川ではなく、川端にたつ一軒の小さなそば屋だった。柳橋裏河岸の「仁八そば」で出会った何とも風変わりな「仲間」たちが、次から次へと巻き起こす上を下への大騒動は、天下の御一新をはさんで、明治なかばに至るまでのじつに28年間におよぶことに
原爆投下から3年後の広島を舞台に、父と娘の精緻な対話が織りあげる、ほのかな恋の物語。しかし核兵器の、人類の存在をも脅かすそのおぞましい力は、可憐な娘の心にも大きな傷跡を残していた。生きる喜びを失くしてしまった娘にふたたび希望の光を蘇らせるために、いま、父は全身全霊で娘に語りかける。