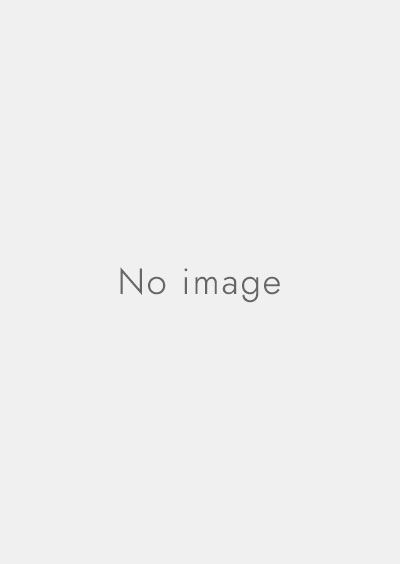死の舞踏には二種類ある。宗教的観念に根ざすDanses des Morts、生き延びた人が死を茶化す要素もあるDanses Macabres。世界中に「死の愛好文化」の遺産がある。どの時代も、多産が飢饉や戦争による大量死と対抗したのだろう。バタバタと愛する者の死を経験し、死によって初めて生が価値づけられ、芸能は痛みを見極めることだと思い始めた。
私の舞踊は最近、神や絶対者のための芸術であるより、儚い生を生きる人間や弱さのための芸能でありたいと考える。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
前衛的な踊りで知られた津田信敏に師事した若松美黄と津田郁子が設立した「若松美黄・津田郁子自由ダンスカンパニー」が、1969年の「回復路線」を皮切りに2009年の「笑いの箱」まで毎年42回連続して行った公演。そのうち「ふり」「村へ帰る」「暗黒から光へ」「ジーキル博士とハイド氏の寓話」が文化庁芸術祭優秀賞を受賞している。
ニューヨークのバレエ教師クビノ氏は、紙を丸めて空中にほおり投げ、「これがバレエだ」と言った。自然の落下そのもののことを。レッスン帰りにオペラハウスの噴水前で踊ったものだ。笛を吹くのは仕事も家もないその日暮らしの自然食主義者。彼の生活が自然の生活ならば、やはり重すぎる。自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらぐ。キドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。それは自然か、不自然か。
イサドラ・ダンカンやトルストイの孫娘との結婚など、派手な人間関係を持ったロシアの詩人セルゲイ・A・エセーニンは‟最後の田園詩人”として自然を詠い、農婦を聖母マリアに比した。自らを「何かから離れる詩人」とみなした束縛を恐れ放浪する天性。そのラストメッセージから『人生は一場の笑、生が偉大なものでないのに、死だけが偉大であり得ようはずがない』と意を汲み、登場人物を道化としてエセ―ニンに対比させている。
タビネズミは異常発生が起こると集団で移動し、時に河などで大量死するという。これは繁殖を適正に調整する淘汰の一種との説をも生み、人類の文化史観に影響を与えている。作品はタビネズミにおける死の舞踏を描く。異常発生の中、突如、舞踏狂が巻き起こる。盲目のネズミ(若松)を除く全群が乱舞し、嬉々として川に飛び込み溺死する。佇む盲目のネズミ。一転、人間に変身。場面は街角。傍らを、幼児の手をひく妊婦が通り過ぎる。
世の中というものが本当に立派なものなら、世の中に根ざした私の悲哀も立派なしっかりしたものであろう。世の中がメチャクチャと思うなら、悲哀も、メチャクチャに分解するものと思いたい。夜も朝も、生まれる前も死した後も、同じように生き残っていくものなのか。作品中、現代のルーツである30年代の悲哀が顔を出す。老化に向かう肉体が抱く嘆き節が、当時の流行にのっかり軽薄にロマン的回顧に滑り込むということなのだろう。