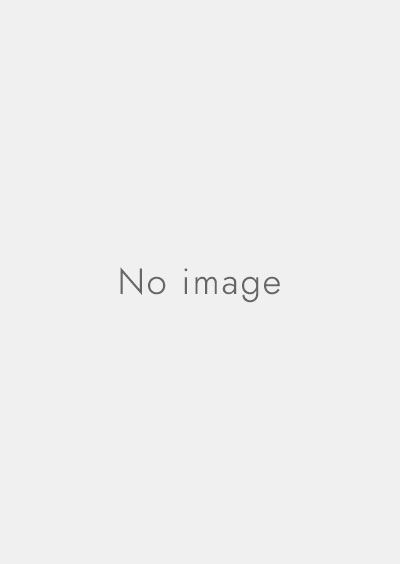折田克子がギリシアメテオラの真っ赤な月を見た際にインスピレーションを受け、創作したソロ作品。針で突き刺すとプシュットはじけそうな真っ赤な月。月の光を通し陰と陽、妖精性から妖艶さ、多様な女性像、宇宙観、生死感、無、等、様々な要素を凝縮させた舞踊作品。作者独自のボディテクニック、間、呼吸等、時に音楽を奏でるような間合い、音楽性は、石井獏そして石井みどりのリトミックの技法が基にあり、折田克子の独自の世界
風に色があるか否かは知らないがうつろう風のなかには、確かにそれぞれの景色が棲んでいる。風の景色を見た時から人は踊りを知る。しあわせなことに景色を見たのが、少年の頃であれば、少年は必ずダンサーになる。だが不幸なことに、知らなければ何事もなく終わってしまったであろう人生のなかばで風の景色を知ってしまった人は哀しい。
折田克子が演出・振付し、泉勝志のダイナミックな構成力とナイーブな細部を見事に引き出している。肉体に共棲する基督と猶太の混沌を最も深刻に自覚する舞踊家、泉勝志にとってこの世紀末に訪れた凪いだ時代は、逆説的にふさわしい。孤高の存在として饗宴を主幹し、舞台で風を切り駆走しなければならない真の悲惨が予定されている。饗宴は招集されたばかりである。
石井みどりの初期の作品に「ひめゆりの塔」があるが、時を経て直接的な表現から抽象的な表現に昇華させた作品が「魂魄」。フォーレのレクイエムを使用した鎮魂の舞で、戦争の悲惨さを憂い、また人々を踊りや音楽で癒したい気持ちが強く表れた作品である。
ストラヴィンスキー作曲「春の祭典」、石井みどりの振り付けはよくある生贄の物語やスペクタル舞踊でない、石井みどりが名曲から得たインスピレーション、「自然と生命力」がテーマとなっている。ダンサーたちの曲線と直線のせめぎあい、重心移動によって運ばれる足、中心から裏へ身体を使うさま、動中の静などがみどころで、身体がとらえる表現の最終章は、みごとな人間讃歌となっている。
折田克子は稀にみるオリジナリティを有した現代舞踊の作家である。新作「タオ」は、79年作の「憶の市」にみられた儀式性を、開かれた場に移している。人間の内側のメカニズムと内在するドラマを、ダンサーと振付者の作業のなかで、外容化し顕現する。それらの交叉するコアで起こり得るものの探索である。タオは過去に記憶をもった異端者達に古代の夢を見、精神を未来に開く。(公演プログラムより)
モーリス・ベジャールに招聘されて渡欧した泉勝志がヨーロッパで活躍後帰国し、初めて発表した作品。サポーターにトゥシューズというスタイルを本作品で確立した。泉は自らが見た夢を数多くの絵画に残していたが、イメージのコラージュが溢れ出る作品となっている。
パッヘルベルのカノンに振付けた群舞。空間に広がりのある振付に時折印象的な仕草が混ざり、裸足の少女達の戯れが清々しい。音楽を伴奏として扱うことなく音楽と溶け合うような一体感のある作品である。
エリック・サティの「梨の形をした3つの小品」を使用し、口をあけて食べる仕草を振付に入れながらも絵画的でロマンティックな作品に仕上げている。
生きながら死んでいる少女は無数に散りばめられたパラソルに紛れ乱舞する…… パラソルは、いつしか真紅の曼珠沙華になりカラカラと風になく風車に…… 十一面観音にみとられ、少女は湖底に横たわり、虚空には夜の月がのぼる。──月をめぐり、くりひろげられる少女と青年の混沌への道行き。形体(フォルム)と混沌(カオス)の本質的な出会いをめざす折田克子のダイナミックな豊穣の世界。
英国の振付師アントン・ドーリンに「こういうものは観たことがない」「この踊りのためにバッハは作曲したのではないか」といわしめた。それが石井みどりのブランデンブルグ・コンチェルトである。石井みどりのこだわりであるリズムの取り方、「溜め」(リズムの裏をとること)から動くこと、「盗み音」があること、「動中の静であること」、これは日本の伝統的な音のとりかたでもある。本作はこれらを象徴する石井みどり作品の代表
石井みどりが戦前に訪れた中国他、様々な夢の断片がコラージュされた作品。“夢はある時、においや色、光、熱の交錯などで夢幻の境地へ誘い、またある時は、まばたきの一瞬の間に想像的な旅となる。”
ーやわらかい月が地球に接近しありとあらゆる硬質な突起を発生させ地球がその本質をあらわにしたころの記憶を人類はほんとうに喪失してしまったのだろうか。
-
思いっきり 潔く すべてを取り払った空間でMIKAのBODY+感性だけによる素描。インプロヴィゼーションの跳躍の間で今現れるミカ・トポロジカル・ダンス・ワールド。
-
横浜ダンスコレクション 1996 バニョレ国際振付賞ジャパンプラットフォーム ナショナル協議員賞受賞作品
「ささやかに幸福(しあわせ)」は1988年初演。60分。ブレヒトの長編詩に導かれ、5組のカップルが繰り広げる人間模様。世の中、予期せぬことは突然やってくる。せめて今の現実を幸せと思おうではないか。「ELCK(エルク)」は1989年初演、40分。オランダ語で「みな・それぞれ」を意味するブリューゲルの同名絵画から発想を得る。「壊れた地球の上に立ちながらこの世の物体に無駄に欲張る人々。」イヴさえリンゴを
死の舞踏には二種類ある。宗教的観念に根ざすDanses des Morts、生き延びた人が死を茶化す要素もあるDanses Macabres。世界中に「死の愛好文化」の遺産がある。どの時代も、多産が飢饉や戦争による大量死と対抗したのだろう。バタバタと愛する者の死を経験し、死によって初めて生が価値づけられ、芸能は痛みを見極めることだと思い始めた。私の舞踊は最近、神や絶対者のための芸術であるより、儚い
誰もが完全な善ではいられない。誰もが内に持つ善と悪。ジキルとハイドは悪の甘美な誘惑に負け罪を犯してしまう。最初は小さな罪を。やがて大きな罪へ。ジキルとハイドの最後は首吊り自殺だ。ユラユラと揺れる身体は善と悪の間で揺れる2人の心のようだ。
アダムとイヴは蛇に勧められ知恵の実を食べ、神の怒りを買う。楽園を追われた人類は、知恵により世界を創り、楽しい都会の生活がもたらされる。人間は変化・進化するが、異常者も生む。暴行を受けた少女は精神を病み両親は苦悩する。医師団はアダムとイヴ、蛇の二重性を持つ。療養の地で少女は蛇を踏み、ショックから快方に向かう。蛇の助けで知の世界に帰る…神話が現代に再生する。人間の喜びが自然と混じりあって表現される。
映画監督ヴィーネによって有名になった「カリガリ博士の箱」をバレエ化した。物語は精神を病んだ男の妄想の話。人体実験をする博士。実験の為に誘拐されてしまう女性。女性を助けようと乗り込んだが捕らえられてしまう男性。実験によって狂わされていく女性と精神を犯されていく男性。最後は病んだ男性が自分は博士だと思い込み博士と女性を殺し、自身も炎にまみれるところで終わる。何処まで事実で何処からが妄想なのか?
博士の生命に対する執着から産み出された不完全な生命体の物語。愛する人の死を受け止められない。愛する人と過ごす幸せな未来を願う人々。生から死、死から生の輪廻の輪から外され壊れていく一人の男。命と云う神秘に見せられ、ただ全てを知りたかった一人の博士。恐ろしく悲しい物語だ。
ニューヨークのバレエ教師クビノ氏は、紙を丸めて空中にほおり投げ、「これがバレエだ」と言った。自然の落下そのもののことを。レッスン帰りにオペラハウスの噴水前で踊ったものだ。笛を吹くのは仕事も家もないその日暮らしの自然食主義者。彼の生活が自然の生活ならば、やはり重すぎる。自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらぐ。キドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。それは自然か、不自然か。
世の中というものが本当に立派なものなら、世の中に根ざした私の悲哀も立派なしっかりしたものであろう。世の中がメチャクチャと思うなら、悲哀も、メチャクチャに分解するものと思いたい。夜も朝も、生まれる前も死した後も、同じように生き残っていくものなのか。作品中、現代のルーツである30年代の悲哀が顔を出す。老化に向かう肉体が抱く嘆き節が、当時の流行にのっかり軽薄にロマン的回顧に滑り込むということなのだろう。
初舞台がレ・シルフィードだった若松にとってシルフィードは青春の響きを持っていた。イサドラ・ダンカンのショパン集をフォーキンが監修、グラズノフやケラーがショパンの曲をバラバラに変造し組曲を創り上げ、ラ・シルフィードをもじってレ・シルフィードと名付けた。これはモダンバレエの始まりでもある。羽衣、シルフィードともに男性の理想だった。理想は現実となった時消え去り、達することのできない理想ほど美しい。