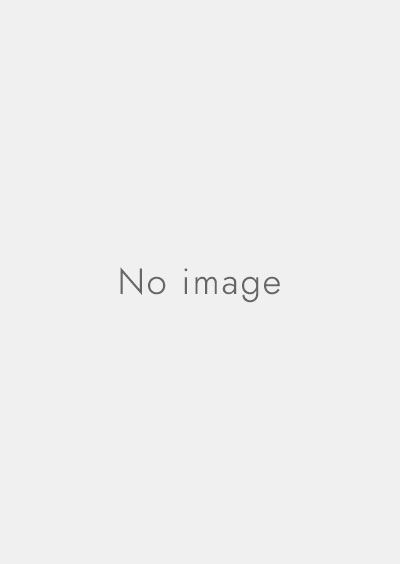ニューヨークのバレエ教師クビノ氏は、紙を丸めて空中にほおり投げ、「これがバレエだ」と言った。自然の落下そのもののことを。レッスン帰りにオペラハウスの噴水前で踊ったものだ。笛を吹くのは仕事も家もないその日暮らしの自然食主義者。彼の生活が自然の生活ならば、やはり重すぎる。自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらぐ。キドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。それは自然か、不自然か。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
前衛的な踊りで知られた津田信敏に師事した若松美黄と津田郁子が設立した「若松美黄・津田郁子自由ダンスカンパニー」が、1969年の「回復路線」を皮切りに2009年の「笑いの箱」まで毎年42回連続して行った公演。そのうち「ふり」「村へ帰る」「暗黒から光へ」「ジーキル博士とハイド氏の寓話」が文化庁芸術祭優秀賞を受賞している。
イサドラ・ダンカンやトルストイの孫娘との結婚など、派手な人間関係を持ったロシアの詩人セルゲイ・A・エセーニンは‟最後の田園詩人”として自然を詠い、農婦を聖母マリアに比した。自らを「何かから離れる詩人」とみなした束縛を恐れ放浪する天性。そのラストメッセージから『人生は一場の笑、生が偉大なものでないのに、死だけが偉大であり得ようはずがない』と意を汲み、登場人物を道化としてエセ―ニンに対比させている。
アダムとイヴは蛇に勧められ知恵の実を食べ、神の怒りを買う。楽園を追われた人類は、知恵により世界を創り、楽しい都会の生活がもたらされる。人間は変化・進化するが、異常者も生む。暴行を受けた少女は精神を病み両親は苦悩する。医師団はアダムとイヴ、蛇の二重性を持つ。療養の地で少女は蛇を踏み、ショックから快方に向かう。蛇の助けで知の世界に帰る…神話が現代に再生する。人間の喜びが自然と混じりあって表現される。
誰もが完全な善ではいられない。誰もが内に持つ善と悪。ジキルとハイドは悪の甘美な誘惑に負け罪を犯してしまう。最初は小さな罪を。やがて大きな罪へ。ジキルとハイドの最後は首吊り自殺だ。ユラユラと揺れる身体は善と悪の間で揺れる2人の心のようだ。
初舞台がレ・シルフィードだった若松にとってシルフィードは青春の響きを持っていた。イサドラ・ダンカンのショパン集をフォーキンが監修、グラズノフやケラーがショパンの曲をバラバラに変造し組曲を創り上げ、ラ・シルフィードをもじってレ・シルフィードと名付けた。これはモダンバレエの始まりでもある。羽衣、シルフィードともに男性の理想だった。理想は現実となった時消え去り、達することのできない理想ほど美しい。