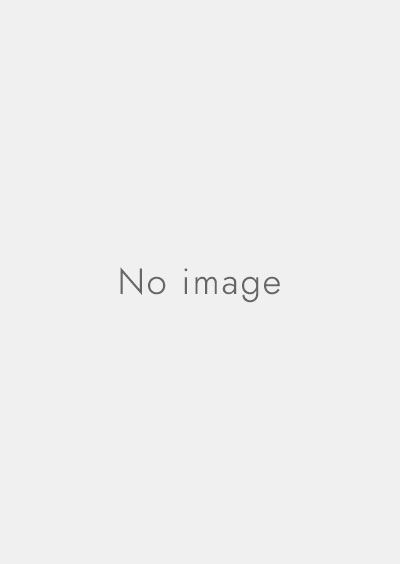(フライヤーより)ダンスシーンも、衣替え!show-case「だんすにGONE」は、あなたの抱いていたイメージをガラリと衣替え!今をトキメク4人の第三世代が、ダンス本来のダイナミズムをそれぞれのエナジーで、それぞれのまったく新しい感覚で発信。さあ、今、あなたの目の前に真新しい鮮烈な輝きが!!
舞人として踊った五井輝が、前年の86年1月に死去した土方巽を追悼した公演。土方を思い出させる赤いスカートなどの衣装や音、音楽が随所に使われた。唇にはルージュを塗りたくり、背中一面に刻まれた風神雷神の入墨を見せ、剣山を自らの肉体に刺す。すべてをさらけ出して極度の集中をもって踊る五井に、「さながら土方の魂が降りたかのようだった」とThe Japan Times Weeklyのレビュー記事(1987年9
(フライヤーより)アメリカからヨーロッパへと発信されたダンスは、いま様々な国で受信されて同時多発な演舞をはじめた。まるで21世紀のダンスシーンを予感させるように‥‥‥…。この〈DANCE SESSION 21〉の新シリーズも受信だけではなく、21世紀へ向けてダンスの発信基地にもなるべく、内外の若い振付家に開放された基地です。世界のダンス・コレオグラファーがその素晴らしい出会いを求めて集う「バニョレ
1985年に開催されたButoh Festival '85にて上演された。プログラムの五井輝の言葉には次のようにある。 「夢うつ太鼓の雄叫びに / 肉は舞えども 心は踊らず / 陽光と陰影の 狭間で揺れる肉体は / 現し世の陽炎 / 形骸と化した肉体は / 醒めた欲望を蜂起する あらかじめ失われた夢から / 解き放された肉体は / 吹き晒しの孤舞となる」 「小懺悔」というタイトルには、肉体を土壌に
死の舞踏には二種類ある。宗教的観念に根ざすDanses des Morts、生き延びた人が死を茶化す要素もあるDanses Macabres。世界中に「死の愛好文化」の遺産がある。どの時代も、多産が飢饉や戦争による大量死と対抗したのだろう。バタバタと愛する者の死を経験し、死によって初めて生が価値づけられ、芸能は痛みを見極めることだと思い始めた。私の舞踊は最近、神や絶対者のための芸術であるより、儚い
男は演出家。家では夫、父、息子。オイディプス演出中に発病し、入院する。癌と疑い、医師、家族、友人に真実を教えるよう迫る。嘘と隠蔽の中、彼はオイディプスと自らの行動を比較。不治と察しつつ、家族の思い遣りを傷つけまいとする。オイディプスに重ね合わせ死を見据えるうち、日本の風土や人情を容認する気持ちになる。クリスマス、友人と家族と共に、そのひと時を心から楽しもうとする。外にはすべての汚れを払う雪が舞う。
イサドラ・ダンカンやトルストイの孫娘との結婚など、派手な人間関係を持ったロシアの詩人セルゲイ・A・エセーニンは‟最後の田園詩人”として自然を詠い、農婦を聖母マリアに比した。自らを「何かから離れる詩人」とみなした束縛を恐れ放浪する天性。そのラストメッセージから『人生は一場の笑、生が偉大なものでないのに、死だけが偉大であり得ようはずがない』と意を汲み、登場人物を道化としてエセ―ニンに対比させている。
開けてはいけない箱を誘惑に負けて開けてしまったパンドラ。箱から飛び出した災いと希望が現代の芸能界を舞台に繰り広げられる。不幸、病気、欲望、絶望、嫉妬などさまざまな災いに見舞われる人々。どん底まで落ちた人々にも最後の最後には必ず希望がある。それぞれの災いを乗り越えて希望へとたどり着く人々。
アダムとイヴは蛇に勧められ知恵の実を食べ、神の怒りを買う。楽園を追われた人類は、知恵により世界を創り、楽しい都会の生活がもたらされる。人間は変化・進化するが、異常者も生む。暴行を受けた少女は精神を病み両親は苦悩する。医師団はアダムとイヴ、蛇の二重性を持つ。療養の地で少女は蛇を踏み、ショックから快方に向かう。蛇の助けで知の世界に帰る…神話が現代に再生する。人間の喜びが自然と混じりあって表現される。
映画監督ヴィーネによって有名になった「カリガリ博士の箱」をバレエ化した。物語は精神を病んだ男の妄想の話。人体実験をする博士。実験の為に誘拐されてしまう女性。女性を助けようと乗り込んだが捕らえられてしまう男性。実験によって狂わされていく女性と精神を犯されていく男性。最後は病んだ男性が自分は博士だと思い込み博士と女性を殺し、自身も炎にまみれるところで終わる。何処まで事実で何処からが妄想なのか?
博士の生命に対する執着から産み出された不完全な生命体の物語。愛する人の死を受け止められない。愛する人と過ごす幸せな未来を願う人々。生から死、死から生の輪廻の輪から外され壊れていく一人の男。命と云う神秘に見せられ、ただ全てを知りたかった一人の博士。恐ろしく悲しい物語だ。
ニューヨークのバレエ教師クビノ氏は、紙を丸めて空中にほおり投げ、「これがバレエだ」と言った。自然の落下そのもののことを。レッスン帰りにオペラハウスの噴水前で踊ったものだ。笛を吹くのは仕事も家もないその日暮らしの自然食主義者。彼の生活が自然の生活ならば、やはり重すぎる。自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらぐ。キドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。それは自然か、不自然か。
世の中というものが本当に立派なものなら、世の中に根ざした私の悲哀も立派なしっかりしたものであろう。世の中がメチャクチャと思うなら、悲哀も、メチャクチャに分解するものと思いたい。夜も朝も、生まれる前も死した後も、同じように生き残っていくものなのか。作品中、現代のルーツである30年代の悲哀が顔を出す。老化に向かう肉体が抱く嘆き節が、当時の流行にのっかり軽薄にロマン的回顧に滑り込むということなのだろう。
初舞台がレ・シルフィードだった若松にとってシルフィードは青春の響きを持っていた。イサドラ・ダンカンのショパン集をフォーキンが監修、グラズノフやケラーがショパンの曲をバラバラに変造し組曲を創り上げ、ラ・シルフィードをもじってレ・シルフィードと名付けた。これはモダンバレエの始まりでもある。羽衣、シルフィードともに男性の理想だった。理想は現実となった時消え去り、達することのできない理想ほど美しい。
ダンスがみたい!
大学卒業後53年。一日に1~2回は笑うから、合わせて四万回近く笑った勘定になる。その笑いを棺に詰めあの世に旅立つ人生を考えています。(若松談)自由ダンスを提唱する若松の、エッセイ風なダンス。地蔵像の前の踊りから始まり、歌あり、詩の朗読あり。客席やバックヤードで弟子達が合唱する。「歌って踊るというのではなく、人生のあがきでもあります。少し言いたいことがあるプリコラージュな身体」夕焼けの中で、一人踊る