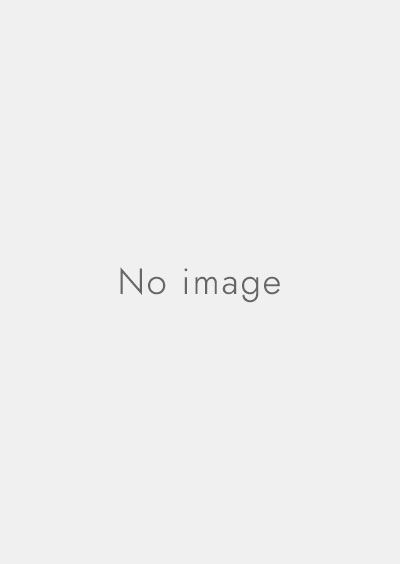日本による韓国併合の時代に朝鮮北部に産まれた李仲燮は、朝鮮の大地を愛し幼い頃より絵に描いていた。一九三五年、支配国である日本に渡り 、東京帝国美術学校、文化学院美術科で絵を学ぶ。在学中に山本方子と出会い魅かれ合うが、戦局も逼迫して一人、実家のある元山(ウォンサン)へと戻った。思いを断ち切れない方子は終戦間近の一九四五年、危険な玄界灘を一人渡り仲燮と再会する。二人は結婚、山本方子は李南徳(イ・ナムドク)として生まれ変わり二人の子どもを授かる。やがて第二次大戦は終結するも朝鮮半島は混乱が続き、朝鮮戦争が勃発。身の危険を感じた仲燮は、芸術と家族を守るため、一人残るという母に絵を託して元山から脱出する。一家は釜山から済州島にたどり着くが、南徳と子共たちは健康状態が悪化、仲燮を残して日本に帰ることとなった……。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
劇団文化座は戦時下の1942(昭和17)年2月26日に結成される。同年4月第1回公演梅本重信作『武蔵野』で旗揚げ。敗戦間際の昭和20年6月、日本の現代劇の紹介という名目で満州に渡り2か月後に敗戦を迎え、一年間の難民生活を経て帰国。以来、「戦争と日本人」にこだわった作品、日本の底辺に生きる人々に寄り添った作品、現代を映す鏡となる現代劇を生み出し続けている。
3・11後、ぼくに出来る、無理のない支援はないものかと思い続けた。二年後の東北を歩き、いまだ津波の残した災害の激しさ、なまなましい景色を眼の前にした。そこで、津波に呑まれて亡くなった人たちの幽霊が、生き延びた人たちを慰めていた話を聞き、ぎりぎりの救いまでも消えていくように、幽霊も出なくなって寂しいという老人のこころに語りかけたいと思った。一人芝居でその悲しみと希望を描けないかと思った時、佐々木愛さ
高井かおると島田とも子、現在51歳。高校時代からの親友であるが、性格も考え方も今まで歩んできた道も正反対。かおるは愛する夫と二人の子供に恵まれ、主婦として平穏な生活を送ってきた。しかし夫の浮気が発覚し、どうしてもそれが許せず一年まえに離婚。とも子は大学卒業後、出版社に勤務、キャリア・ウーマンとして独身を通してきた。しかし彼女も出版社の倒産という憂き目にあう。そんな人生のターニングポイントを迎えた二
感動の浅田次郎作品、初の舞台化! 「鉄道員(ぽっぽや)」「壬生義士伝」「蒼穹の昴」など数々のベストセラーを世に送りだし幅広い年齢層の人々に圧倒的な支持を受けている浅田次郎氏。その作品群の中でもひときわ光彩を放つのが「天国までの百マイル」です。同作品はすでに映画化、ドラマ化されています。そして今、文化座が挑む初の舞台化。親子の深い絆、男女の切ない恋、そして人と人との出逢い。<愛と勇気と再生>の物語を
古典的先住民姿の少女が語る、いつとは知れない、しかし先祖代々伝えられてきた物語ーその年は天候不順で食糧の蓄えができないまま厳しい冬がやってきた。危機に瀕した集団のリーダーは、口減らしのため、お荷物となっていた二人の老女を棄てる決定を下す。それは老人を敬い大切にする伝統に背く決断であった。彼らは食糧を求めて旅立っていく。棄てられた二人の老女は、悲しみ、恨み、怒り、そして絶望の淵に立たされる。しかし死