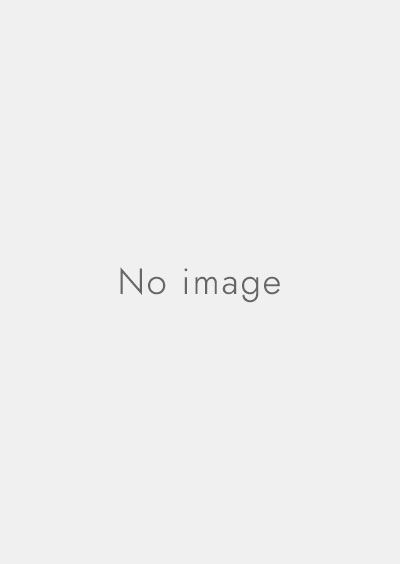一人の女性が成長していく過程を軸に、鏡のなかにみる“自己”という存在と他者の“眼差し”から見える自己存在との矛盾を軸に、“世界/全体”からみた自己と他者の入子構造を描き出し、”世界/全体”と個との調和と関わりについて無限に映し返す。ラヴェルの組曲「鏡」の作曲から100年を経て再解釈。音楽をヴィジョンとして読み解き、身体と映像を通して、音楽の向こう側にある物語を視覚表現とともに翻訳する。
今回の公演タイトル「Antipiol(アンティピオル)」は、「分裂症の少女の手記」(セシュエー著)の本のなかで実際に病院で腫物に使われていた軟膏の名前。少女は精神疾患で入院中に聞こえた幻聴の声をアンティピオルさんと呼ぶ。嘲笑し命令する声のアンティピオルとの闘い。彼女だけでなく誰でも心の中にある自分でもわからない感情、押さえつけられた思い、トラウマなどが何かのきっかけでアンティピオルのように現れるも
「菓」は植物の生態からインスパイアされたものをテーマとし、坂田有妃子の父親の死に感じた想いも重ね合わせた。たとえば植物が成長していくときに出す「エチレン」というフェロモンは、秋の紅葉など葉が色づく現象を起こす。それは目には見えない植物同士の信号のようで、ささやいている言葉のようにも感じ、そして植物同士の猛烈な競争や駆け引きが起こっているようにも捉える。繰り返す生死をミクロの視点から切り取り作品にし
滑稽かつ批判的な眼差しから日常を切り取り、都市における無意識の振る舞いを人・物になって自在に演じてきたオル太が、2020年東京オリンピックを目前に、京都で初となるスタンドプレーを上演します。新国立競技場の構造モデルから設計したスタジアムを劇場に再現し、「自らが演じること」と「演じることを観ること」が演者と観客、都市と劇場のなかで入れ子構造で立ち上がり、人間の共存に結びついてきた行為を問いかけます。
ニッポン・イデオロギー
ヴィジュアルアーツ/パフォーミングアーツの制度との折衝、社会学的/民俗学的フィールドワークを重ね、挑発性とユーモアを併せ持つ活動を展開するアーティスト集団「オル太」が、「ニッポンのイデオロギー」がとる日常的形態のパフォーマティブな分析に6つの切り口で取り組みます。「取り止めのない一つの感情のようなものが、現在の日本の生活を支配しているように見える[…]日本に限らず現在の社会に於けるこの切実で愚劣な
ニッポン・イデオロギー
ヴィジュアルアーツ/パフォーミングアーツの制度との折衝、社会学的/民俗学的フィールドワークを重ね、挑発性とユーモアを併せ持つ活動を展開するアーティスト集団「オル太」が、「ニッポンのイデオロギー」がとる日常的形態のパフォーマティブな分析に6つの切り口で取り組みます。「取り止めのない一つの感情のようなものが、現在の日本の生活を支配しているように見える[…]日本に限らず現在の社会に於けるこの切実で愚劣な
2010年2月に開催された第2回恵比寿映像祭「歌をさがして」で参加展示した、藤本隆行/Kinsei R&Dのインスタレーション作品『Time Lapse Plant 4 Rings』に於いて、一度限り行われた、男性現代舞踊ダンサー4人による即興ダンスの記録映像。舞踊手は、川口隆夫・白井剛・鈴木ユキオ・森川弘和の4名。
旧人類は500万年間進化しなかった。そこに現人類が現れ、他種の殺戮をはじめた。手や知識が「力」となり、創意工夫が文明を発展させていく。やがてヒトは全能な力を崇拝する共同体となり、同じ力(神)を信じない者への弾圧は残虐を極めた。そこで、他者との共存を図るため「寛容」という概念が生まれる。共同体はしだいに国家となり、暴力を独占していく。武器は、鈍器なものから鋭利なものへ発達し、弾丸となりやがて情報とな
福島原子力発電所の爆発事故と、それに続く日本政府を含めた核発電所を取り巻く状況に驚きと後悔を感じて、改めて情報や知識、知恵という概念を捉えようと試みた作品。振付に白井剛を、中心となる砂漠の老人には舞踏家の吉本大輔を迎え、音楽はヴァイオリニストの辺見康孝が舞台上で演奏を続け、パフォーマーの川口隆夫・平井優子・カズマ グレンと共に、幾人ものプログラマーが映像・音響ともに関わり、舞台を作り上げている。
(フライヤーより)多極配分された諸力の組曲としてくるみ割り人形を弄ぶ—再び—厳密に稀少な—ラベルとして—通底機として—諸断片の異質性—として後から計算する機械従って—累積する—精確な多角形の—方法—など贋の平衡とサチュロス—虚集合—華やかな二元化装置及び—モナド—など—反復する異形の—散逸する—寛大な—カバン劇—無関心—水準器など—分布図など—中空の箱の中の奇麗な頂点—を—公正に蘇生する
-1997年フランスでレジデンス制作し初演されたパフォーマンス作品。舞台は何も無い真白な空間で、半円筒形に張られた白いスクリーンだけで構成される。強力なストロボ照明によるホワイトアウトの創出と強烈な音響・映像。「自己と非自己のボーダー」「生と死の間に横たわるグレイ・ゾーン」などに関するさまざまな考察が試みられた。 グループのリーダー的存在だった古橋悌二が、1995年の死の直前に書き残した次回作のコ
“pH”とは、物質の酸性/アルカリ性の度合を示す用語。パフォーマンスは二項対立の図式にそって13のphases ー 問い/答え、イメージ/言葉、事実/虚構、拡張/圧縮、公/私、現実/非現実、攻撃/防御、緊張/弛緩、生産/再生産、男/女、外/内、そして最後に第一場と最終場に共通する開始/終焉/再開 ー から構成されている。細長いパフォーマンス・エリアの両側2階の客席から観客は舞台を覗き込むように見下
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021の「エリア50代」で初演された、笠井叡振付・平山素子のソロダンス『J.S.バッハ作曲“フーガの技法”1.2.6.9番によるダンス』が、スケールアップして再誕!クラシック、jazz、ポップス…と様々なフィールドで活動を展開する、片山柊(愛知公演)、佐藤浩一(横浜公演)という2人の若手ピアニストを迎え、ダンスと音楽で『フーガの技法』とい
世界と向き合うために:基本的に「虚構/お芝居」である事が前提の舞台上で展開される、『true/本当のこと』というパフォーマンスは、何が嘘で何が真実かという話ではありません。知らぬ間に自分も捕らえられているかも知れない閉塞感を振り切って走り出すために、「現実」のどれほど多くの部分が、あなた自身によって作り出されているのかを、改めて問い直すためのものです。
世紀を隔ててなお人類を震撼させる核の恐怖を真のあたりに感じることになった3/11にインスピレーションを受け、マイケル・マゼドンの『100000万年後の未来』をサブテキストに、地球的時間のスパンで人類の進化と現在、そして核と抜き差しならない関係を結んでしまっている人類の困難を描く。更に三好達治、茨木のり子の詩を引用。