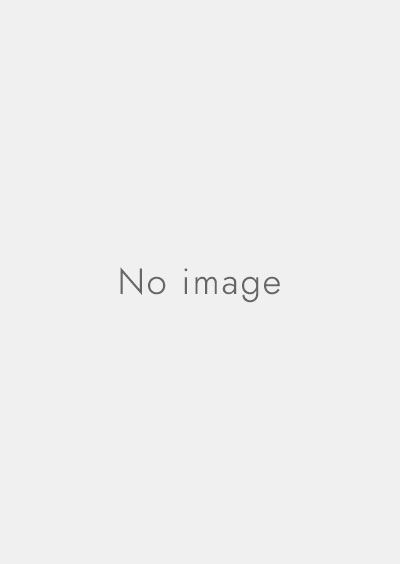■あらすじ
太古より山に住む謎のいきもの・獸(ケモノ)。
〈青い山〉と〈白い山〉の間を走る、大きな谷の集落に住む山のひとびとは、獸ととくに接することなく、しかし存在は常に感じながら、日々共に生活してきた。
あるとき、獸ははじめて人を殺す。
憤った集落の男たちは討伐に向かうが、皆返り討ちに遭う。
生き残った数少ない者たちは獸を恐れ、集落を捨てて山を降りる中、猟師・シラスは鋭い目で森を睨みつけながら 山を登り続ける。
彼には引き返せない理由があった。
最初に殺された人間は、彼の子供・リシリであった。
その 20 年後。啓蟄を迎え、山に緑が溢れ始めた春の頃。
シラスは依然として山を徘徊し、獸を探し求めているが、その姿を捉えることができない。
■ステートメント
私たちはカタストロフの中心地にいる。現在、COVID-19は人間より上位に立ち、私たちの生活を制限し、命を奪う。その関係の終わりがどこにあるのか。目を凝らしても、霞がかった時代は明瞭な答えを映し出さない。改めて自然、そして地球というものは人智の及ばぬ存在であり、人の万能さは幻影なのだと感じる。
現代人は、支配されることに慣れていない。狩られる側としての心詰まりがない。なぜなら脳を使い、技術力を高め、動植物をコントロールすることで、ツリー・オブ・ライフの外側に移動したからだ。先祖のたゆまない努力と蓄積のおかげである。
しかしその進歩の陰で、産業革命以降、異常な速度で地球上を侵食し、環境を一変させ、多くの植物や動物を絶滅に追いやってきた。例えばサンゴは海水温の上昇で白く染まり、やがてドロドロに溶けていく。例えば農地へと開墾するため森を刈り上げ、そこで暮らしていた生物を排除する。他者を犠牲にして、自身の生活を豊かに変える。その繰り返しの果てが今の地球の姿だ。
私は支配することも、されることも疲れた。
もちろん、その相互関係が完全になくなることはないだろう。自然災害は起きるし、人間は誰かの命を食べなければならない。生きているということは、互いの存在と影響し合うことなのだから。
しかし、どのように関わりながら生きていけるか、他者を無視せず、その可能性を探し、思いを巡らせ、そしてより良い道を選択することはできるはずだ。
成長志向が限界を迎える世界。私はその先の未来を思考するために、自然と人間の関係のあり方を再考し、過去・現在・未来に問いかける場を築く。
大きな天災や人災を前にして、アーティストは「芸術はこの出来事に対してなにができるのか」と自問することだろう。私はこの作品が、その問いかけに対しての一つの応答になることを目指す。
演劇博物館別館6号館3階「AVブース」にて視聴可能です。
オンデマンド配信。事前に会員登録が必要です。(月額1,045円)
劇作家・演出家の柳生二千翔が代表する演劇ユニット。2013年から2021年まで活動。劇空間と外部環境をシンクロさせ、物語が鑑賞者の生活と地続きに繋がっていく作風が特徴。正しい/間違い、良い/悪いなどと単純化されない、“世界への新しい眼差し”を提供することを試みる。
2016年、第4回せんだい短編戯曲賞大賞受賞。2018年、本多劇場「下北ウェーブ2019」選出。同年、第1回人間座田畑実戯曲賞受賞。
DRIFTERS SUMMER SCHOOL ADVANCE 2013
『小さな足掻きが世界を変える』をコンセプトに、映画と演劇を同時進行で展開するパフォーマンス作品。舞台奥では筋書通りの映画を上映し、舞台上では筋書から逸脱する物語を上演。二重構造の物語が交錯し、予定された未来と抗う意志がぶつかり合う。重なり合うシーンを通して、鑑賞者に小さな勇気が未来を変えることを伝える。演劇ユニット・女の子には内緒の旗揚げ公演として制作された。
下北ウェーブ2019
本多劇場主催「下北ウェーブ2019」にて選出・上演。初演(題『うたたね姫』)は2014年、松戸市での滞在制作を通し、再開発される街と、そこに適応できない人々の姿を描いた。再創作版では、かつて自ら書いた戯曲に共感できないという違和感を出発点に、普段の知覚外にある社会事象を扱った。「その程度で悩むな」という意見の暴力性と向き合うことで、見えにくい痛みや、世界の多様性をあぶり出した。
「街」と「街」の境界が、住民や通行人の多数決で日々変動する時代を描いたSF作品。特徴の乏しい場所はどの街にも属さず、宙ぶらりんの隙間として残されている。その隙間に暮らす文子は、恋人の斎藤から結婚と隣街への引っ越しを提案され、迷っていた。そんな中、空き巣の塩村が部屋に侵入し、私物を少しずつ持ち去っていく。やがて時間の流れと共に、変動する境界は街の隙間さえも飲み込もうとしていた。